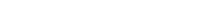Q&A
-
1.補助金交付申請に関して
-
2.令和2年度第3次補正予算と令和3年度の補助金対象施設
-
3.設備及び工事に関して
-
4.計画変更等承認申請書、届出書に関して
1.補助金交付申請に関して
【補助金交付申請書の書式】
- 補助金交付申請書の書式はどのような書類で提出すれば良いのですか。
- 令和2年度第3次補正予算の公募より申請方式が従来の方法から大きく変わります。申請書は本ホームページにある「申請の手続き」内の「申請書類一式」からダウンロードしていただき、作成した申請書一式を本ホームページにある「申請書類の提出はこちら」のDropboxへアップロードして提出いただきます。
申請書はすべてExcel形式(振興センター指定様式)になっており、入力シートへの入力方式となっています。また、各様式書類への捺印を廃止します。
申請書の提出に際しては、入力シートにより記載をした「災害バルク補助金Excelファイル」とPDFに変換した様式第1とその他添付書類を、それぞれ各フォルダーに保存した上で、その申請フォルダーを本ホームページのDropboxへアップロードして提出いただきます。
詳しくは、当センターホームページに掲載の『本年度の事業について』、『申請の手引き』、『説明動画』、『Dropbox使い方説明画像』及び『業務方法書』、『業務細則』を確認願います。
【補助率】
- 補助金の補助率を教えてください。
- 申請者(共同申請者が補助対象設備設置施設の運用・維持・管理者である場合は共同申請者)が業務方法書第3条第3号に規定する「中小企業」に該当する場合は、補助対象経費の2/3以内、該当しない場合は1/2以内となります。ただし、一時避難所となり得るような施設(地方公共団体が災害時に避難所として協定等を締結した施設)の場合には、中小企業であっても1/2以内となります。
また補助金には交付限度額があり、申請する設備によって上限が設定されていますので詳しくは『本年度の事業について』、『業務方法書』をご覧ください。
【中小企業】
- 申請者が補助金申請で定める中小企業者の確認方法を教えてください。
- 「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用します。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
ただし、次のいずれにも該当しない必要があります。①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている。
➁交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている。
※業務方法書第3条第3項を確認願います。
【医療施設、福祉施設の認知】
- 内科・小児科病院は地方公共団体の認知が必要ですか?
- 医療施設、福祉施設における認知不要の施設とは、災害時に避難所まで避難することができない人が多数生じる施設ということで、原則として、入院病棟や入所宿泊のできる施設・設備があることが条件です。但し、透析クリニック、保育所、障がい者施設、デイケアサービスセンター等は地方公共団体の認知は不要となります。
※保育所は厚生労働省管轄の施設であり福祉施設に含まれますが、0歳児(避難困難者)がいることが条件となります。
【地方公共団体の認知が必要な施設・不要な施設】
- 地方自治体の認知が必要な施設、不要な施設を教えてください。
- 業務方法書第4条第2項第3号③に定める、地方公共団体の認知が必要な「一時避難所となり得る施設」の例は以下の通りです。
認知が必要な施設 認知が不要な施設 病院(入院施設なし) 病院(入院施設あり) 事務所、店舗、商業施設 透析クリニック 幼稚園 保育所(0歳児がいること) 学校(私立) 学校(公立) 工場、倉庫等 公的避難所等 老人ホーム・障がい者施設 デイケアサービスセンター 注:詳しくは業務方法書第4条第2項第3号及び『申請書記載説明』を
確認ください。※認知を取得したとしても、申請を行う設備が業務継続のBCP対策設備とならないよう、一時避難所として運用するために必要最低限の能力のものとすることが必要です。
【公的避難所への食料供給施設】
- 食料品用倉庫の食料を災害時に公的避難所へ供給する契約を地方公共団体と締結していますが、冷蔵庫用自家発電設備に使用するLPガス供給設備及びLPガス発電ユニットは補助対象と認められますか。
- 災害時に一時避難所とならない施設は補助金を受けられません。
食料品等を供給支援する「物資支援協定」等では、地方公共団体の認知を受けたことにはなりませんので、必ず一時避難所としての認知を受けてください。
【駐車場】
- 駐車場は一時避難所として認められますか。
- 駐車場だけでは避難所として認められません。屋内に避難できる施設等に付属していることが条件です。
屋内に避難できる民間施設の場合は、地方公共団体(市区町村)の認知が申請時までに必要となります。
【3日間以上運用できるLPガスの備蓄量】
- 3日間以上運用できるLPガス(石油)の備蓄量とは、どのくらいですか。
- 提出された(別紙9)「燃料消費量計算書」により確認します。
設置予定のLPガス災害バルク等において、常に維持すべき備蓄量をその設置容量の50%とし、その量で災害時に使用すると想定される設備(機器)の3日間の稼働消費量の合計が賄える量であることを確認し、3日間運用可能な備蓄量とします。
併せて、(別紙9)「燃料消費量計算書」に書かれた災害時に使用する設備の運用については、(別紙10)「災害時における一時避難所の運用について」で具体的に記載していただき、避難時の使用設備消費量の妥当性を確認します。
【同一敷地、同一施設の複数建物】
- 同一敷地内にある、同一施設の建物が複数ある場合の交付申請は、1物件で申請か、2つの物件として個別に申請するのか、教えてください。
- 同一敷地、同一施設の複数建物の場合は、同一案件として、上限額も1案件の扱いとなります。
但し、同一敷地内であっても、別施設であれば、2つの申請として受け付けます。
(例 : A社会福祉法人が、同一敷地内にB医療施設とC老人ホームを持っている場合は、B医療施設とC老人ホームそれぞれ個別で申請が出来ます。)
【一法人による複数申請】
- 一法人が、住所の違う複数の建物を申請することは出来ますか。
- 一法人が、住所の違う複数の建物を申請することは可能です。その場合、それぞれ申請書を作成し、申請してください。
(例:社会福祉法人が、東京都港区、鹿児島市、札幌市、大阪市にある介護施設4カ所がある場合、それぞれ申請することができます。)
【地方公共団体の認知】
- 民間施設を一時避難所とする場合の地方公共団体の認知とはどのようなものですか。
-
地方公共団体が災害時にその民間施設を一時避難所として活用できることを認知していることが明確にわかるもので、その民間施設に係る補助金の申請者と地方公共団体(市区町村)との協定書やその民間施設が地方公共団体のホームページで災害時の一時避難所として掲載されているなどが典型例です。また、申請時までに地方公共団体(市区町村)に認知がされていることが必要です。
補助事業者側から地方公共団体に提出した書類に担当部署の受番や受領印のみが押されたものは、地方公共団体組織としての意思が不明確であり、実際に災害時に活用できるかどうかが不明確なため、認知していることが明確とは言えません。
【自治会(町内会)の協定書】
- 民間施設を一時避難所とする場合の認知は、自治会(町内会)の協定書で認められますか。
- 自治会(町内会)との協定書は、地方公共団体による認知ではありません。
災害バルク等を設置する予定の施設名が記載されている自治会(町内会)との協定書を、「地方公共団体が認知している」と振興センターが確認できる書面を申請時に提出するすることにより地方公共団体の認知として認めます。
【事業発注、事業完了時に必要な手続き】
- 補助事業の発注及び事業完了時に必要な手続きについて教えてください。
-
補助事業の発注及び事業完了時に必要な手続きとその期限は、次のとおりです。
工事発注: 交付申請書の審査が終了し振興センターより交付決定を通知する日(交付決定通知書の日付)以降、発注ができす。交付決定通知日より前に発注したものは補助対象とはなりませんのでご注意ください。 事業完了: 最終期日令和4年2月15日(厳守)までに事業を必ず完了(全ての支払いを完了)させ、実績報告書をその事業の完了日(最後の支払いを完了した日)から30日以内(厳守)に提出してください。事業完了日が令和4年1月30日から2月15日までの場合は、実績報告書を令和4年2月末日(厳守)までに提出することが必要です。
申請時の事業完了日記載にあたっては、事業経費の支払完了までの補助事業実施期間の遅延可能性要素を想定した上で、適切な事業完了日の設定をしてください。
【補助金交付申請書の申請内容の間違い、不備等の軽微な修正に関して】
- 補助金交付申請書の申請内容の間違い、不備等軽微な修正に関して、振興センターはどの様に対応するのですか。
- 交付申請書受理後、審査し不備により修正が必要となった場合は、振興センターでは修正を行いません。振興センターより申請者に、指摘事項をメール又は電話にてご連絡をいたしますので、申請者ご自身で指摘事項を修正をし、メール添付により振興センターへ再提出していただきます。
なお、単なる書類上の間違い、不備ではなく、交付要件等に合致しない申請内容であることが判明した場合は、補助金交付申請は不採択となります。
【申請者の実務担当者、履行補助者の役割】
- 実務担当者、履行補助者とは、どのような立場でしょうか、役割を教えてください。
- 実務担当者は申請者の代理として補助金交付申請書、実績報告書作成の担当者であり、履行補助者は、申請者の依頼で実務担当者の補助員として作業を行う役割を担っているにすぎません。このため、実務担当者は、補助金交付申請書、実績報告書等すべての内容を理解しておく必要があります。振興センターからの問い合わせに対し実務担当者から適切な答えが得られない場合、審査不能として不採択となる場合があります。
なお、実務担当者も履行補助者も業務方法書第27条に基づく補助事業実施に伴う情報管理及び秘密保持義務がありますのでご注意ください。
【申請書類作成前に準備する決算関係書類】
- 申請書類作成前に準備が必要となる決算関係の添付書類を教えてください。
-
①法人の場合は、決算報告書(直近2ヶ年分)・登記事項証明書(申請日より3ヶ月以内に取得したものであること)。新設の社会福祉法人は直近2ヶ年の決算書提出ができなくても構いませんが、新設等で前年度の決算書がない事業者は申請できません。
②法人以外の場合(以下の③に該当する者は除く)は、納税証明書(その2)を直近2ヶ年分
地方公共団体は決算書の提出は不要です。③自治会及び区分所有マンション管理組合にあっては、規約・決算書(直近2ヶ年分)。
④その他振興センターが提出を求める書類。
詳しくは、『申請の手引き』をご覧ください。
注1)上記の書類が提出されない場合は、原則として申請することができません。
注2)提出された決算書で、債務超過の場合は申請することができません。
【申請者名・代表者名の記載と登記事項証明書】
- 申請者名・代表者名等の記載について注意することを教えてください。
- 申請者名・代表者氏名及び役職名並びに住所等は登記事項証明書と同一に表記してください。俗称、略名、通称、並びに仮名等に記載誤りがある場合は、受け付けられません。
なお、登記事項証明書等の公的機関の証明書類は、申請日より3か月以内のものを提出してください。
【他の補助金】
- 本補助金の公募に申請する施設を経済産業省以外や地方公共団体の補助金にも申請する予定ですが、申請できますか。
- 本補助金の公募に申請する対象設備や工事費等を、他の国(経済産業省以外の省庁)の補助金と重複して受け取ることはできません。なお、地方公共団体(都道府県及び市区町村)からの補助金に関しては、本補助金と地方公共団体からの補助金の合計金額が、工事総額を超えなければ申請できます。(地方公共団体の補助金の重複受給については、当該地方公共団体にご確認ください。)
詳しくは振興センターに問合せ願います。
【補助対象期間】
- 大型施設の新築物件へLPガス災害バルク等の導入を行う場合、施設の工事施工期間が長期にわたることから補助事業期間を超えてしまう可能性があるが、年度内に完了しなければいけませんか。
- 令和4年2月15日までに事業が完了できない場合は、交付決定を受けた案件であっても、最終的に補助金が出ないことになります。
また、新築案件に関しては、補助対象設備を設置する施設が、事業完了日までに建物が竣工していることが必要となります。補助金事業は単年度事業ですので、こうした新築案件の場合、新築部分の完成スケジュールを十分精査し、施設完成後に補助金を申請、交付決定後にLPガス災害バルク等の導入の発注・工事を行うなど、当該補助金を申請する年度内に完成することが確実なタイミングで補助金の申請をしてください。
【リース】
- リースによる申請でも補助金の対象になりますか。
- 対象になります。この場合、申請者はリース会社となり、施設を運営、維持、管理する者は共同申請者となります。補助金の率は、共同申請者が中小企業に該当する場合は2/3以内、該当しなければ1/2以内となります。但し中小企業であっても、一時避難所となり得るような施設(地方公共団体が災害時に避難所等として協定等を締結した施設)の場合には補助率は1/2以内となります。
中小企業に該当するかどうかについては『Q&A』【中小企業】の項目を参照ください。
【転リース】
- 避難所を運営又は管理する者に転リースする場合は、補助の対象となりますか。
- 補助の対象とはなりません。
【「国土強靭化地域計画」「地震防災対策強化地域等」とは】
- 「国土強靭化地域計画」「地震防災対策強化地域等」とは
- 国土強靭化地域計画についてはこちらをご確認ください
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/tiiki.html
地震防災対策強化地域等についてはこちらをご確認ください
 地震防災対策強化地域一覧
地震防災対策強化地域一覧
(詳細は業務細則第9条第1項第2号に記載)
2.令和2年度第3次補正予算と令和3年度の補助金対象施設
【申請する予算年度における補助対象施設の違い】
- 令和2年度第3次補正予算と令和3年度とでは、補助対象施設に違いがありますか。
- 令和2年度第3次補正予算では、多数の避難困難者が発生する「医療・福祉施設」「公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)」が対象となります。
令和3年度では、令和2年度第3次補正予算補助対象施設に加えて「民間商業施設等の一時避難所となり得るような施設(地方公共団体が災害時に避難所等として協定等を締結した施設)」が対象施設となります。※詳しくは『業務方法書』第4条及び『申請書記載説明』をご確認ください。
【LPガススタンドの申請】
- LPガススタンド(オートガススタンド)の補助金申請について教えてください。
- 令和2年度第3次補正予算・令和3年度予算ともに、LPガススタンド(オートガススタンド)は補助対象とはなっていません。
3.設備及び工事に関して
【見積依頼・見積書】
- 見積書は3社以上必要ですか?
- 補助事業を行うにあたり、売買、請負、委託その他の契約を締結するときは、原則、競争入札(又は3社以上の相見積)により発注先を選定してください。(入札者が3社に満たない場合、申請書提出時に業者選定理由書を提出していただきますが、相当の理由と認め難い場合は、補助金の対象とはなりません。)
【見積書・見積明細書作成】
- 見積書及び見積明細書作成に関して注意すべき事項がありましたら教えてください。
- 見積書(設計見積含む)及び見積明細書の記載内容に関しては、設置する機器毎に設備費・設置工事費別に、またそれぞれを補助対象・補助対象外に区別し、設置する機器毎に設備費と設置工事費の合計金額が判別出来るように記載することを入札業者に作成依頼して下さい。また申請書には、補助対象設備機器は型番(品番)ではなく容量や能力で記載しますが、見積明細書に記載する補助対象設備機器は必ず型番(品番)を記載して、その内容での見積書を申請書に添付して下さい。また見積に際しては、主要設備であるバルク容器、ガス発電機、GHP等の出入荷見通しを確認願います。(申請時での発注は行わないでください。交付決定前の発注は補助対象外となります)
また見積書の有効期限は、交付決定までの期間を考慮して「6ヶ月」を目途に記載をお願いします。
【設計見積書】
- 地方自治体として補助金申請する場合には、申請時には設計見積書の提出になりますが、作成に際して注意すべきことを教えてください。
- 地方自治体が作成する設計見積書内容に関しては、設置する機器毎に設備費・設置工事費別に、またそれぞれを補助対象外・補助対象外に区別し、設置する機器毎に設備費と設置工事費の合計金額が判別できるように作成してください。また必要経費(設計費等の諸経費)は補助対象・補助対象外にかかわらず原則全て計上をして、主要設備毎の設備費と設置工事費、補助対象経費と補助対象外経費の関係が明確になっている設計見積書を作成して下さい。入札後に提出する計画変更等届出書において、申請時の設計見積書に記載されていない追加工事費、未計上経費は認められませんので注意して作成してください。
【申請書(設計図面、計算書等)作成、公共機関への届出書類作成等の費用】
- 申請書類作成、事業完了後の公共機関への届出書類作成等の費用は補助対象になりますか?
- 補助事業は、交付決定を受けてからの発注、工事請負契約をもって開始日としています。従って、交付決定前に実施した申請書の作成に係る、LPガス、電気の設計図面作成、計算書種類等の費用は、交付決定前の費用となりますので補助対象とはなりません。交付決定日以後の図面作成、公共機関への届出書類作成等の費用は補助対象です。
【新築工事案件】
- 補助対象設備を設置する建物が新築案件である場合の注意事項について教えてください。
- 補助事業の目的に鑑み、補助対象設備を設置する建物が、事業完了日までに竣工されることが条件となります。新築案件の場合には、申請時に竣工日の明記をしていただきますが、竣工日が令和4年2月15日を超える場合には今年度での申請は出来ませんのでご注意願います。また申請いただいた竣工日が変更になる場合には、振興センターに直ちにご連絡をいただき、計画変更手続きについて協議して下さい。ただしこの場合でも令和4年2月15日を超えての変更手続きは認められませんのでご注意願います。
【複合施設工事の一部申請】
- 補助対象の施設を含む複合施設に関して申請する場合、補助対象施設工事を複合施設工事から分けて単独で発注すれば補助対象として認められますか。
- 複合施設工事とは別途に、災害バルク等の設置に要する補助経費として単独に見積書が作成され、その経費内容が見積明細書で明確に示されており、申請する工事が未発注であれば補助対象となります。
但し、補助事業の発注先は、原則「競争入札」による選定が必要ですので、複合施設工事発注先の指名とせず、3社以上の入札で発注先を決定しなければならないことに注意してください。
また、当該複合施設が新築案件である場合は、令和4年2月15日までに建物が竣工していることが必要となります。
【解体、撤去工事】
- 災害バルク、GHP等の入替工事に発生する、既存のバルクや付随設備等の解体、撤去及び廃棄費用は補助対象になりますか。
- 既存バルク容器や付帯設備等を含む既存設備の解体、撤去等及び廃棄費用は補助対象とはなりません。
【足場及び養生】
- 足場組み立てや破損防止の養生は補助対象費用として認められますか。
- 補助対象工事に係る付属の足場や養生は補助対象ですが、補助対象外の工事に係るものは補助対象とはなりません。
【基礎工事】
- バルク容器のコンクリート基礎工事と防護柵等は補助対象となりますか。
- 何れも補助対象となります。
バルク容器の地上設置は、コンクリート等の基礎、若しくはバルクベースへの設置は補助対象となります。また、地下埋設用砂搬入や設置工事等の土木工事は、設置工事費として補助対象になりますが、必要最低限のものとしてください。オーバースペックの基礎や美観重視の防護柵は補助対象とはなりません。
【障壁】
- バルク設置に係る火気との距離確保のための障壁は、補助の対象となりますか。
- 補助対象となりますが、必要最低限のものとしてください。
【LPガスシリンダー容器の購入】
- LPガス供給業者より、シリンダー容器で供給する場合は、その容器及び供給設備は供給業者が用意すると説明されましたが、容器や供給設備を購入する必要がありますか。
- シリンダー容器で供給する場合においても、申請者がシリンダー容器及び供給設備の購入をすることが補助金の条件です。
シリンダー容器でLPガスを供給する場合は、申請者が新品50kgシリンダー容器6本以上を必ず購入してください。また購入したシリンダー容器に関しては、LPガス販売事業者及び配送事業者と「容器寄託契約書」を必ず締結してください。
購入したシリンダー容器は、(様式第22)取得財産等管理明細書記載の処分制限期間中は適切に維持管理することが必要となります。
【容器収納庫】
- 50kgシリンダー容器での供給の場合、容器収納庫は補助対象となりますか。
- 補助対象となりますが、必要最低限のものとしてください。その容器収納庫に容器以外のものを置いてはいけません。
【バルクの複数設置またはバルクとシリンダー容器の設置】
- バルクの複数設置またはバルクとシリンダー容器両方の設置は認められますか。
- 災害時に3日間以上の補助対象設備を稼働する消費量の合計が賄えるLPガスを確保するために、必要であればバルク容器の複数設置またはバルク容器とシリンダー容器の複数設置は認めます。この場合、複数設置による複数系統の配管であっても、同一建物への供給であり尚且つ各供給設備が同一敷地内に設置されている場合に限り、10口ガス栓収納ボックス(防滴型)の複数設置は不要です。また、新規のバルクやシリンダー容器と既存のバルクやシリンダー容器を併せて接続することで、3日間以上の補助対象設備の稼働を確保することも認めます。
なお、別紙9の「燃料消費量計算書」で災害時に3日間以上の補助対象設備の稼働を確保できることを示す必要があります。
【GHP】
- 自立型ではないGHPは補助対象設備になりますか。
- 自立型ではないGHPは、災害時電源が途絶した場合、稼働しないので補助対象設備になりません。ただし、LPガス発電機または他の自立型GHPから電源が確保できれば、補助対象となります。
【GHP設置における補助対象の工事範囲】
- GHP設置における補助対象の工事範囲を教えてください。
- 室外機設置(基礎、運搬等を含む)、室内機取付、冷媒配管、通信線、LPガス配管の工事(バルク容器からの非常用の専用配管のみ)は補助対象内の設置工事になります。電気工事は補助対象とはなりません。
室内機の設置は、災害時に避難困難者のいる施設や一時避難所を維持するために、振興センターが必要と認めた範囲について補助対象となります。避難場所以外のエリアに設置する室内機は補助対象となりません。
【電気工事設備の補助対象となる範囲】
- LPガス発電機の電気配線工事は、どこまでの範囲が補助対象となりますか。
- LPガス発電機から電源切替盤までの電気配線工事が補助対象となります。
また、建物付属設備や外灯型の非常用照明機器(LED照明等)及び非常用コンセント等は補助対象外となります。
詳しくは、『本年度の事業について』をご覧ください。
【スプリンクラー設備に利用する発電機】
- 災害時に一時避難所で使用する電気機器と共にスプリンクラー用ポンプにも電源供給する発電機を計画していますが、補助対象と認められますか。
- スプリンクラー設備を主に稼働するための発電機は、防災のためのBCP対策としての発電機となりますので、補助対象とはなりません。
【給湯器】
- 給湯器、ボイラーが補助対象となる要件は何ですか。
- 災害発生時に電気や水道等のライフラインが途絶した時、3日間以上使用できる電源と水が確保できれば、補助対象となります。
その場合、電源確保のためのLPガス発電機は補助対象ですが、水を確保するためのポンプや貯水槽等は補助対象とはなりません。
【コジェネレーション】
- 災害時にお湯は使用できないものの発電機としては使用できるコジェネレーションは補助対象と認められますか。
- 認められますが、コジェネレーションは熱(お湯)と電気を同時に供給するための器械ですので、災害時に熱が使用できない仕様のコジェネレーションの設置は、災害対策としてはオーバースペックであるため、補助対象とは認められません。
【移動できる燃焼機器等収納場所】
- 移動できる燃焼機器等(移動式LPガス発電機、炊出しセット、鋳物コンロ、ガスストーブ等)の保管場所に関するルールはありますか。また、そのための収納庫は補助対象となりますか。
- 移動式のLPガス発電機、LPガス燃焼機器ユニット(調理器具、炊出しセット、鋳物コンロ、ガスストーブ等)は、災害時のほかは、点検又訓練時以外の使用はできません。災害時に損傷を受けず、災害時でも速やかに使用できる場所に保管してください。
ただし、そのための収納庫等は補助対象とはなりません。また補助対象となる容器収納庫に保管しないでください。
4.計画変更等承認申請書、届出書に関して
【設置機器変更による補助金の減額】
- 補助事業における施工上、または補助事業者(申請者)の都合により、申請時に補助対象とした機器の一部設置を取りやめることは出来ますか。
- 補助事業は交付決定を受けた時の事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)で実施することが原則ですので、何らかの計画変更が生じた場合、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。その上で、やむを得ない事情で補助対象機器の一部の設置を取りやめる等で交付決定金額よりも減額になり、申請時に提出した(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」の変更が必要と判断された場合は、変更に伴う補助事業を実施する前に、予め振興センターに相談の上、(様式第7)計画変更等届出書を提出するか、(様式6)計画変更等承認申請書に変更後の見積書等を添付して振興センターに提出することで承認を得られれば、機器の一部設置を取りやめることはできます。
【設置機器の補助金額が変わらない他社同等品への変更】
- 納期遅れ等で、設置予定機器を他社同等品に変更する場合で、交付決定金額の変更がない場合、計画変更の手続きは必要ですか。
- 補助事業で何らかの計画変更が生じた場合は、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。その上で、補助対象機器のメーカー・種類は変更になるものの、機器の能力・数量・見積金額及び事業完了日にも変更がなく、申請時に提出した(様式第1)「交付申請書」の記載内容及び(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」にも変更が生じない場合には、(様式6)計画変更等承認申請書や(様式7)計画変更等届出書の提出は必要ありません。
【計画変更等承認申請書】
- 業務方法書第15条第1項に定める計画変更等承認申請書が必要となる場合やその手続きについて、具体的に教えてください。
- 補助事業者が交付決定後に補助事業を実施する中で、やむを得ない事情で交付決定を受けた時の事業内容(機器のメーカー・種類・数、設置工事内容等)が変更になり、交付決定額(設備費・設置工事費)に変更が生じ、申請時に提出した(様式第1)「交付申請書」の記載内容に変更が生じる場合、また申請時に提出した(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」の内容等が変更になる場合は、(様式第6)計画変更等承認申請書を、原則として、その計画変更を行う事業の実施前までに申請し承認を受ける必要があります。ただし代表者の変更については、事業の推進に影響がない場合には(様式第7)計画変更等届出書にて届け出てください。
事業の中止や補助金申請の取り下げをする場合には、(様式第6)計画変更等承認申請書での申請提出が必要となります。
過去の補助事業実施においても様々な事例がありましたので、補助事業で申請内容から何らかの計画変更が生じる可能性が発生する場合は、微細な事項であっても自己判断をせずに速やかに振興センターに相談してください。
【計画変更等届出書】
- 業務方法書第15条第1項但し書きにある「軽微な変更」について、具体的に教えてください。
- 業務細則第13条第2項各号にある「補助事業の目的変更がなく能率的な実施に資する場合」や「補助事業の目的や能率に関係がない細部の変更」ということになりますが、当振興センターでは、交付決定を受けた事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)に変更がなく、申請時に提出した(様式第1)「交付申請書」及び(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」の記載内容に変更が生じないことを前提としています。こうした前提に沿う、何らかの軽微な変更が生じた場合(例えば、「事業完了日」のみ遅れが生じる場合)は、(様式第7)計画変更等届出書を提出していただく必要があります。
補助事業で申請内容から何らかの計画変更が生じる場合は、自己判断をせずに速やかに振興センターに相談してください。
 (見本)災害時における一時避難所等施設利用に関する協定書
(見本)災害時における一時避難所等施設利用に関する協定書